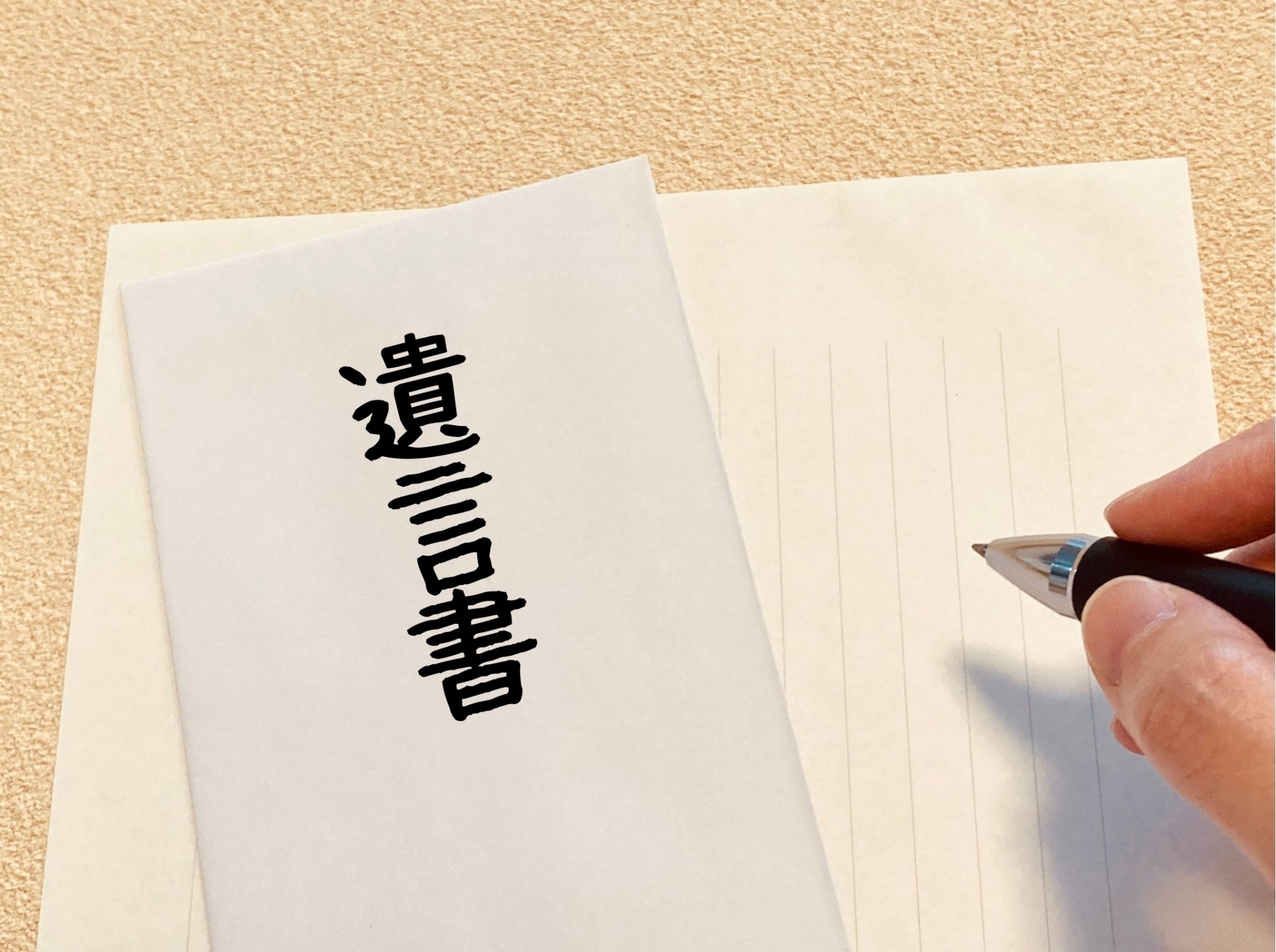被相続人が生前に遺言書を作成している場合は相続が発生すると基本的に遺言の内容を基に遺産分割を行うことになります。
遺言書はすべての相続財産について記載することが多いですが、一部の財産について記載することも可能です。では、遺言書に記載のない財産についてはどのように対応したらよいのでしょうか。
当記事では遺言に記載のない財産の分割方法や注意点について解説します。
遺言書に記載のない財産の対処方法
遺言書に一部の財産のみ記載がある場合、記載がある財産については遺言のとおりに相続し、記載のない財産については相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
一部の財産についてしか記載がない場合、問題があるので無効になると考える人もいるかもしれませんが、一部だけ記載する遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言を作成する際でも有効な遺言となります。
自宅の不動産や事業に利用している土地など一部の財産について誰が相続するか決めるというケースもありますが、価値の高い不動産など一部について記載がある遺言はかえってトラブルとなり関係が悪化する事例もあります。
例えば、長男と長女が相続人となるケースで自宅不動産を長男に遺すとだけ遺言に書かれているような状態では、金融資産を平等に分けるべきだと考える人もいるでしょうし、自宅不動産を長男が引き継いでいる分金融資産は長女が多く相続するべきだと思う人もいるでしょう。
最悪の場合は本人同士では解決できず、弁護士や法律事務所を通して交渉となる場合もあります。遺言書どおりにわけると法定相続分と大きく乖離するケースや遺留分を侵害するケースは注意が必要です。実際に相続が開始した後に不完全な遺言が見つかったことでかえって家族に負担がかかることも多いので、遺言書の書き方や文言について不安な場合は司法書士など実務の経験がある人に相談してみるのも良いでしょう。
あえて書いていない場合もあれば、記載漏れとなっているケースもあります。記載漏れとなっているケースでも同じように相続人全員で誰が相続するかを決めることになりますが、記載漏れが原因でトラブルになることもあります。
そのため、遺言書を作成する際は財産の記載漏れが無いように預貯金のある銀行、株式を預けている証券会社、不動産などあらゆる財産と取引している金融機関について一覧の表にまとめておく必要があります。
また、遺言書に財産を受けとるように指定された人が相続放棄をした場合でも同じように相続人で協議して決めることになります。
相続に関するお悩みは専門家に相談を
相続に関する相談は専門家に相談することをおすすめです。特に相続税の申告が必要な場合は財産の特定や評価額の確定、遺産分割協議、税金の計算や申告書の準備という流れで行いますが、原則被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の制度は複雑で知識が無い人が自分で行うことは難しく、親族が亡くなった後は不動産の登記や預金口座の名義変更など他にも手続きがある中で対応することは難しいでしょう。自分で手続きを行うことが難しい場合は税理士等の専門家に依頼することも可能です。
広島相続税相談テラスでは相続を中心の業務を行っており、経験豊富な税理士があなたのお悩みを解決します。初回の相談無料で対応しておりますので、お気軽にメールやお電話でご連絡ください。