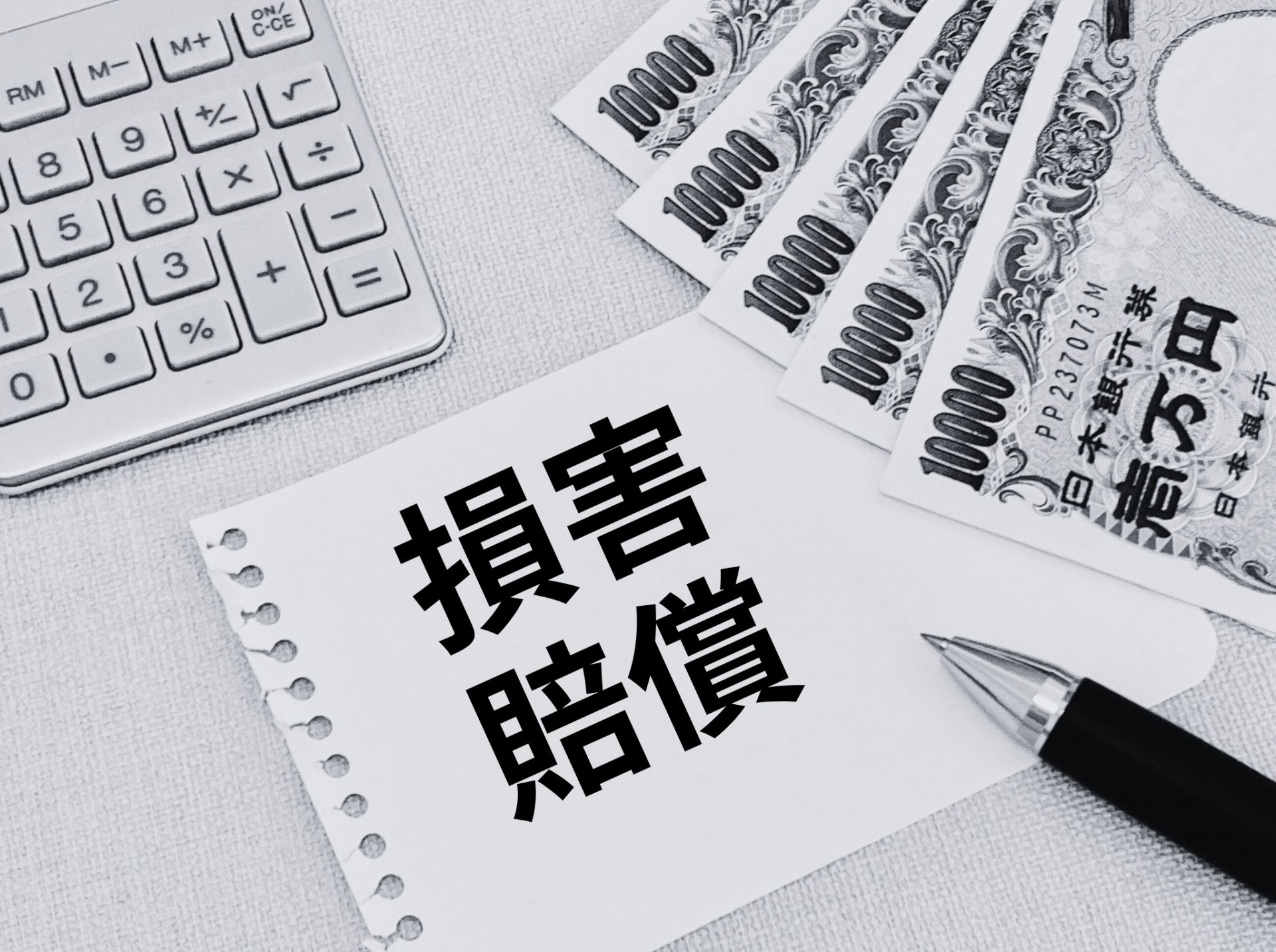被相続人が亡くなると、法定相続人で財産を分けることになります。しかし、相続人で分けるのはプラスの相続財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。
では損害賠償責任を負っている場合はどのように対処すればよいのでしょうか。当記事では損賠賠償責任を負ったまま亡くなった人の相続人がどのように対応するべきなのかを注意点もあわせて解説します。
被相続人が損害賠償責任を負っているケース
被相続人が損害賠償責任を負っているケースの代表的な例はスピード違反による交通事故で自己の過失の程度などにより本人は亡くなっているものの加害者として他人に損害を与えている事例が考えられます。
故意ではなくても事故を起こしてしまい、他人の車を壊してしまった場合や怪我をさせてしまった場合など被害があった場合は通常は事故を起こした者が法律に基づいて金銭での損害賠償や慰謝料を請求され、弁償することになります。保険金である程度賄うことができますが、大きな事故であった際は賄いきれない可能性もあるでしょう。
しかし、事故と同時に死亡してしまった場合、民法で定められた法定相続人が相続財産を引き継ぐとともに債権者への返済義務や損害賠償責任等の債務も引き継ぐことになります。
相続放棄により損害賠償を免れることも可能
原則としては親や配偶者などが生前に事故を起こしてしまった場合、子どもなどの相続人が損害賠償責任を承継することになり、支払う義務が生じますが、プラスの財産よりも損害賠償責任の方が大きい場合、相続放棄の申述書が受理されると被害者からの損害賠償責任から回避することができます。相続放棄をする場合は家庭裁判所で3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。そのため、期限には十分に注意して進めるようにしましょう。また、財産を処分してしまった場合、単純承認したものとみなされて、損害賠償を免れることができなくなります。
ただし、相続放棄をすると自宅の不動産など一切の相続権を失います。相続放棄をして一部の被相続人の名義となっている資産を別に遺産相続するということはできませんので遺産について預貯金、株式、土地・建物、金など内容と額をまとめて一覧にして相続放棄を行ってもよいかよく検討してから裁判所での手続きを進める必要があります。
自分が放棄をすることで、次の順位の相続人など兄弟姉妹など誰か他の親族が責任を負うことになります。自分が相続放棄をしたことで問題になることは多く、トラブルになると弁護士を通じて話し合いをする必要が生じるなど、解決することにも手間と費用がかかります。関係が悪化し、トラブルに発展することを防ぐためにも相続人にも伝えてから裁判所に申し立てるようにましょう。
財産の調査に時間がかかり、プラスになるかどうかわからないという場合は限定承認という方法もあります。限定承認はプラスの財産の範囲で債務を弁済する制度です。限定承認は相続人全員の合意が必要となりますので、一人でも反対すると選ぶことができません。
また、遺産分割は遺言がある場合は基本的に遺言書の内容に沿って行われますが、急な事故によって多額の損害賠償責任を負うこともあります。相続発生後の相続人の判断で相続放棄をすることは可能です。
相続人自身が負う損害賠償責任は免れることができない
被相続人が負っている損害賠償責任は相続人が相続放棄をすることによって免責することが可能ですが、相続人自身が損害賠償責任を負っている場合は相続放棄を行っても支払いを免れることはできません。
例えば、認知症となり成年後見制度を利用している人や未成年者など監督者であった場合は監督者である家族にもその責任が及ぶ場合があります。また、自身が相続人が主たる債務者となっている借金の連帯保証人など保証債務を負っていた場合も相続放棄によって免れることができません。
多額の債務を負い、自分の預貯金などで賄いきれない場合は自己破産という方法もあります。
手続きを専門家に依頼することも可能
不動産の登記など相続財産の名義変更に関する手続きや書類の作成でお悩みや不安がある場合は弁護士、司法書士、税理士など第三者に依頼することも認められています。自分で手続きをすることが難しい場合は専門家にサポートを依頼すると安心です。
特に相続放棄や相続税の申告など期限があるものについては自分で行うことが難しい場合は専門家に依頼することをおすすめします。
相続税の申告は課税の対象となる財産の評価を行い、相続税法で定められた計算方法で税金を算出しますが、制度が複雑で慣れていない人が計算することは簡単なことではありません。また、税理士に依頼することで特例などをうまく活用し、節税につながるというメリットもあります。
広島相続税相談テラスでは初回の相談は無料で対応しております。経験豊富な税理士が多数在籍しておりますので、お気軽にメールやお電話でご連絡ください。