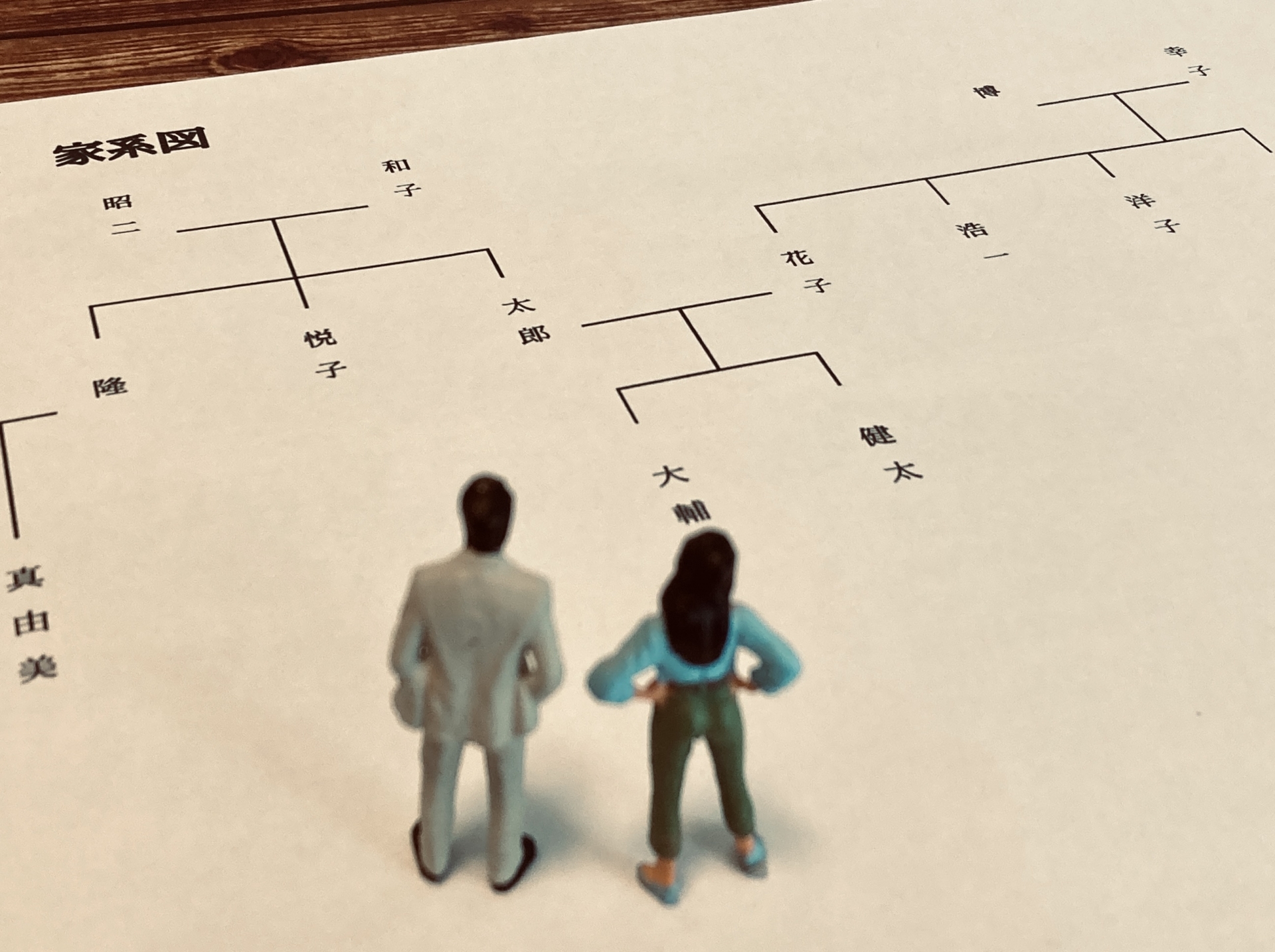相続が開始すると、基本的に法定相続人全員で法定相続割合を基準に協議のうえ遺産相続を行うこととなり、財産を分け合うことになります。相続人は配偶者や子、親や兄弟姉妹(甥・姪)と順位が決まっていますが、親族が誰もいないという人もいるでしょう。
当記事では相続人がいない場合の財産の行方と対処法についてポイントをおさえて解説します。
相続人不存在で相続が発生した場合
民法で定められた法律上の相続権を持つ人がいない状態や、財産を相続する権利を持つ家族がいたとしても何らかの理由で全員が相続放棄をした状態や、他にも子どもなどが廃除されたことにより相続人がいなくなった状態で、代襲相続人もいない場合を相続人不存在と言います。相続人不存在の状態で、死亡した場合の財産は特別縁故者との関係が考慮され、財産分与されるケースがあります。
特別縁故者とは被相続人とは戸籍上の婚姻関係ではないものの、生計を一にしていて実質的な配偶者であるいわゆる内縁関係にあった者や療養中に最後まで介護や看護していた者等、特別な関係にあった人のことです。
特別縁故者の存在もなかった場合は国庫に帰属されることになります。国庫に帰属されるまでの流れは相続財産管理人が選任され手続きを進めることになります。
財産を調査し、借金があり債権者がいないか、官報で債権申立ての公告、行方不明の相続人捜索の公告を行います。そのうえで、相続人不存在であることが確定し、最終的に特別縁故者も現れなかった場合は国庫に帰属され、国の財産になるという流れになります。
遺言書で指定することも可能
上記のような相続人不存在で、誰かに財産を遺したい場合は、事前に遺言を作成することで、指定の人に全部または一部の遺産を遺すという意思を示すことが可能です。
遺言で指定することで、個人だけでなく法人を指定することもできますので、お世話になった団体や、学校などに寄付することも可能です。ただし、不動産など管理が必要な財産については受け取ってくれない可能性があります。人気の地域で、駅に近くアクセスのよい不動産であれば受け取ってもらえる場合もありますので、事前に何を取得することができるか、確認してから遺言を作成するようにしましょう。
被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、遺言により遺贈を受けた受遺者は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内と短い期間で相続税の申告を行う必要があります。相続発生後の手続きは忙しくあっという間に時間が過ぎてしまいます。取引の金融機関など財産の内容に関する情報がないと、手続きができないため、財産の概要がわかるように土地・建物、金融資産、金などの現物資産を一覧の表にまとめて遺言書と一緒に保管しておくと良いでしょう。
遺言書の作成方法には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は気軽に自分で作成できるというメリットはありますが、相続発生後に、必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。相続発生後形式不備で無効となった場合は遺言書通りに分けられない可能性もあります。
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言で作成時に法律上有効であることが確定します。費用と手間はかかりますが、公正証書遺言で確実に作成したほうがよいでしょう。
また、遺言を作成する時に執行者を定めることも可能です。執行者とは遺言の通りに遺産分割を行うために必要な事務手続きに関する権限を与えられた人のことです。執行者は遺言書に基づいて不動産の登記や金融機関の名義変更を行うことができます。執行は専門家に依頼することもできますが、報酬を支払うことになりますので、対応に必要な費用や業務の範囲を事前に確認しておくようにしましょう。
相続に関するお悩みは専門家に相談を
相続人がいない場合の相続は本当に複雑で大変なものになりますので、生前に対策が必要です。遺言書を作成する場合でも内容や書き方に疑問が生じるケースもあるでしょう。
相続発生後不備があった場合は遺言書通りに財産を分けることができませんので、しっかりとした遺言を作成しておくことが重要です。
自分で作成することが難しい場合は税理士や司法書士、弁護士などのサポートを受け、確実な遺言を作成するようにしましょう。また、相続税の申告が必要な場合、計算や添付する書類を準備することは簡単ではありません。申告を誤ったり怠ったりすると税務署から指摘され、加算税を請求される可能性があります。
期限内に自身で間に合わせることが難しい場合は普段から相続税の申告を業務として扱っている税理士に相談し、手続きを進めるようにしましょう。
広島相続税相談テラスでは相続関連の手続きを専門的に扱っており、知識と経験が豊富な税理士が多数在籍しておりますので安心してお任せいただくことが可能です。初回の相談は無料で対応しておりますので、専門家に依頼することを検討している方はぜひお気軽にご相談ください。