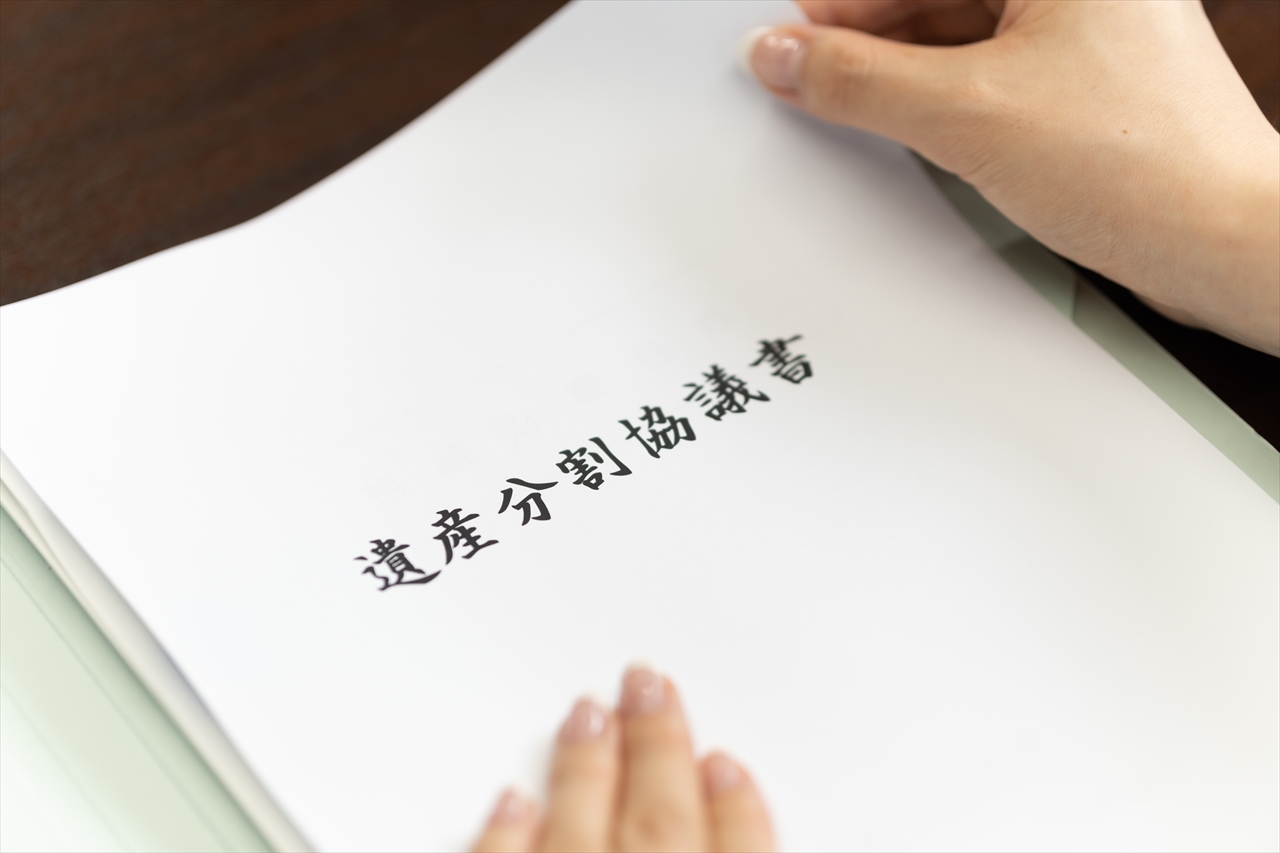相続が発生し、遺言書がない場合は、遺産を分割する際に必要な書類として遺産分割協議書という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に遺産分割協議書を見たことも作成したこともなく、作り方がわからないという方も多いでしょう。当記事では遺産分割協議書を作る際に注意点や必要書類について解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは預貯金や株式、投資信託、不動産等の遺産の分割をするための方法や割合を記載する書類です。遺産分割は相続放棄をした人を除き、法定相続人全員が参加して納得いくまで話し合いを行い、合意のもと作成する必要があります。
遺産分割協議は相続人自身で内容を決める必要があります。法定相続分を基準に話し合いをすることになりますが、不動産など評価が高く分割しにくい財産を保有していることも多いため、必ずしも法定相続分通りに分けられるわけではないでしょう。
協議をした結果をふまえて手続きを進める必要があるため、決められた割合や誰が何を相続するかを親族間で話し合った内容を記載する書面が遺産分割協議書です。
法定相続人は親族関係によって異なりますので、被相続人との関係によって配偶者や親、子(亡くなっている場合は孫)、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)が相続人となります。子どもが先に亡くなっている場合は孫が代襲相続によって相続人となることがあります。人数が多くなり負担が多くなる事例もありますが、遺産分割協議書は相続人全員で話し合いを行った結果を記載し、署名と印鑑を押印する必要があります。
相続人が一人の場合は放棄により財産を相続する人がいない限り遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺言書がある場合は遺言どおりに分けることになるため、基本的に遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産分割協議書に添付しておく書類
遺産分割協議書には必ず添付するべき書類が定められているわけではありませんが、一定の書類を添付しておくことでスムーズに手続きを進めることができます。
どのような書類を添付しておくとよいのか具体的に解説します。
財産の一覧
遺産分割の手続きを進めるうえで、情報として確認しておきたい事項の一つが被相続人が保有していた相続財産です。そのため、銀行に預けている口座の残高や証券会社に預けている株式、土地・建物などの不動産、金や貴金属類、自動車など各財産を一覧の表にした財産目録を作成して添付しておくとよいでしょう。また、預金の残高証明書や不動産の所在地がわかる登記簿謄本も添付しておくことでより詳細に確認することができます。
遺言がない場合は先に話し合いを行い、その後、遺産分割協議書の作成という流れで手続きを進めていきます。話し合いの時に全財産を把握しておいた方がよいので、先に作成することをおすすめします。また、相続税の申告の際にも使用します。
戸籍謄本
相続手続きにおいては法律で定められている法定相続人を確定させることも重要です。現在や過去の結婚や離婚した経緯、夫婦関係や親子関係等、親族の状況を戸籍で確認することができます。
戸籍謄本は親族関係を示す公的な書類で生まれてから死亡までの連続した戸籍を取得することで、相続人が誰かを示す証明書となります。法務局での不動産の登記や金融機関で名義変更の手続きをする際に相続人が誰かを示すために、出生から亡くなるまでの連続した戸籍を集めるのに加え、被相続人が亡くなっていることを確認するための除籍謄本も提出する必要があります。
戸籍謄本は本籍地で保管されていますが、最寄りの市区町村役場で取り寄せて郵送で取得することが可能です。既に確定した戸籍は有効期限はありませんので、親や配偶者の遺産相続の時に使って書類の一部を流用できることもあります。再度取得すると手数料がかかりますので、過去に役所で入手した戸籍がある場合は、確認しておくとよいでしょう。
印鑑証明書
遺産分割協議書には遺産の分割について法定相続人全員で合意したことを記載し、全員で署名・捺印を行います。捺印は印鑑登録を行っている実印で行うことが多く、印鑑証明書を用意することで確かに相続人本人が押印しているということが証明することができます。
印鑑証明書は市区町村役場で請求すれば発行してもらうことが可能で、住所も記載されているため、身分を証明することにも利用することができます。
相続手続きにお困りの場合は専門家に相談を
遺言書の作成や資産をまとめた一覧を作成するなど事前の対策がされていなかった場合、遺言書の有無や通帳がどこにあるかも把握できておらず、財産の調査や分割方針の話し合いや名義の変更など多くの手間がかかることになります。相続人同士で考えが異なることでトラブルになった場合は、話し合いや弁護士など、相続人以外の人にアドバイスを受けたり間に入ってもらったりしても解決することが難しく家庭裁判所での調停や審判で決着するケースもあります。
また、仕事などで忙しく、平日に市区町村役場や金融機関の窓口に行って手続きをすることが難しいという方も多いでしょう。特に相続税の申告期限は10ヶ月以内に税務署への提出と現金での納付が義務づけられており、期限が短いため、複雑な計算を含め申告書の作成を行う必要があり、相続発生後早めに対応を始める必要があります。
財産を取得する者が作業を進める必要がありますが、自分や家族の中に手続きをする人がいない場合は税理士などの専門家にサポートを依頼することを検討することをおすすめします。専門家に依頼することで、相続人の代理人として専門家が進めることができるので、時間を短縮して正確に申告を行うことができるというメリットがあります。
また、自宅に保管する自筆証書遺言や公証役場で作成する公正証書遺言などの書き方や生前の対策について検討する際も専門家に相談することで安心して進めることができます。
広島相続税相談テラスでは実績豊富な税理士が多数在籍しており、さまざまな相続に関するお悩みのご相談に対応しております。初回のご相談はサービスで無料で対応しておりますので、お気軽にお電話やメール等でご連絡ください。