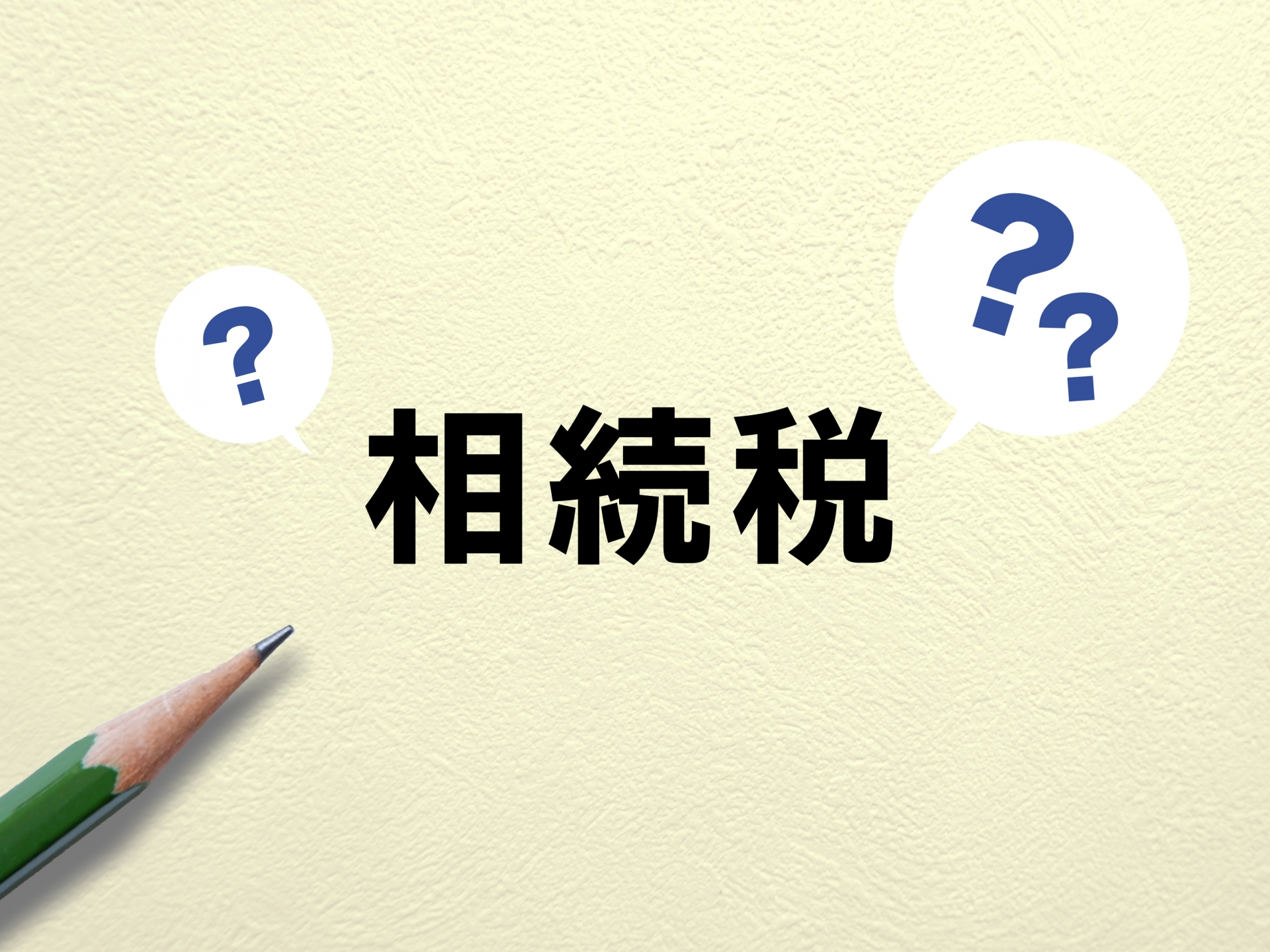相続が発生した際に、被相続人の財産が基礎控除を超える場合は相続人に相続税は支払う義務があります。財産が多く、相続税がかかりそうな場合、相続税について詳しい情報を得て対策をしたいと考える人も多いでしょう。
しかし、税金の制度は複雑で、一般の人にはなかなか理解できるものではありません。税務について詳しい人が身近にいない場合でも誰かが代表して進める必要があります。
誰に相談していいか、選び方がわからないという人も多いのではないでしょうか。当記事では相続税に関する相談相手やそれぞれの特徴についてご案内します。
相続税の相談ができる相手
相続税の相談相手とはどのような人がいるのでしょうか。具体的に紹介します。
税務署
税務署の窓口では相続税の申告にあたって、不明点がある場合に、地域を管轄している税務署相談することが可能です。特例の内容や、利用可否の確認や、計算方法の確認をしたい場合は、に税務署の職員に相談してみるとよいでしょう。
税務署は計算方法などについては丁寧に対応してくれますが、税務署は節税の提案などをすることはありません。節税について相談したい場合は税務署に相談しない方が良いでしょう。
国税局の電話相談センター
国税局とは正しく、税金の支払いがされているか、全国の税務署を監督する立場の機関です。国税局には電話相談センターが設けられており、電話で税金に関する疑問点を確認することができます。
ただし、国税局の電話相談センターでは節税についての提案をしてもらうことはできませんし、電話での相談となりますので、資料を見せながら説明することはできません。具体的な土地の評価額などを確認したい際は別の人に相談することができるでしょう。
税理士会
税理士会とは税理士として業を営む人が所属している組織です。税理士会が主催している、無料相談会では税金に関する一般的な相談の対応をしています。
税理士会が主催する相談会では、節税のアドバイスを受けることもできますが、税理士会の相談は事前予約制で時間も30分程度で決められていることも多く、個別具体的な相談をすることは難しいでしょう。実際に節税対策を一緒に進めていくためには税理士会で紹介してもらった税理士と契約をして進める必要があります。
税理士事務所・税理士法人
税理士事務所・税理士法人でも初回の無料相談に応じているケースが多くあります。税の知識が豊富な税理士に相談できるうえ、税理士は節税のアドバイスをもしてくれます。ただし、税理士にも専門分野がありますので所得税や法人税よりも相続税や関連のある贈与税を多く取り扱っている税理士に相談する必要があります。税理士を探す際にはホームページで確認するとよいでしょう。
専門性のある人の知識も踏まえて、節税のアドバイスを受けることで、大きく節税できる場合があります。
税理士に正式に手続きなどの対応を依頼する場合は報酬を支払う必要がありますので、先に費用を確認してから契約するようにしましょう。
税理士に相談する際の流れ
生前に自身の相続税の対応に関する相談をする際に、どのような流れで相談を行えばわからないという方も多いでしょう。相続対策までの準備について一般的な流れについて解説します。
まずは現状把握
相続税の相談をする際は、節税の具体的な方法検討するより先に状況の把握をすることが大切です。相続税には基礎控除があり、3,000万円+600万円×法定相続人で計算します。
財産の総額が基礎控除以下で、相続税がかからない場合は、そもそも節税対策をする必要がありません。法定相続人の範囲と預貯金や株式、不動産など各財産の評価額を確認し、一覧の表を作成したうえで将来、自分が亡くなった時に相続税がかかりそうかを確認するとよいでしょう。株式や不動産など時価によって変動する財産がある場合は、実際に支払う税金とは異なりますが、シミュレーションをして目安を確認しておくことは重要です。
分け方を検討する
相続税の対策を行ううえで、財産の分け方を考えることは非常に重要です。配偶者控除や小規模宅地の特例等相続税には各種特例や控除があり、誰が何を相続するかによって実際に支払う税額が大きく変わる制度となっています。
そのため、相続発生前に配分を決めておくことで、トラブルを避け、スムーズに財産を受け、税金の計算をするこができます。生前に遺産分割の方法を事前に決めておくことは節税をするうえでも大切なことです。
内容をしっかりと整理して決めておきたい場合は、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
具体的な節税策を検討する
現時点での相続税の計算をすることができたら、実務に詳しい税理士のサポートを受けて具体的な対策を検討するとよいでしょう。
相続税対策には生命保険の非課税枠の活用や、年間110万円の基礎控除を活用した生前贈与、不動産を活用した対策などさまざまな種類があります。資産の内容や家族構成によって個別に検討する必要がありますので、実績の豊富な税理士のアドバイスを受けて、検討する方が良いでしょう。
申告も税理士に依頼することが可能
実際に相続が発生すると、原則10ヶ月以内に申告手続きを完了させる必要があります。
相続税の節税のアドバイスを受けて手続きをした場合は、その税理士に、実際の相続が発生した時の税金の申告手続きも依頼することが可能です。自分でも申告はできますので、必ず頼まないといけないわけではありませんが、事前にアドバイスを受ける際に、財産の内容や法定相続人の構成も伝えているため、ポイントがわかっており、申告書類の作成もスムーズにできるというメリットがあります。
相続税の計算ミスをしてを間違って提出してしまうと、税務調査で指摘されてしまう可能性もあります。期限の後で調査によって誤りを指摘されると、通常よりも高い加算税を課されるリスクもあります。税務署は過去に支払った所得税や固定資産税などを把握しており、想定よりも少ない場合は調査をする可能性が高いです。
節税のアドバイスだけでなく、申告書の提出も依頼することでスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
節税のアドバイスは税理士に相談を
ここまで解説した通り、国税庁のサイトに、掲載されている計算方法など一般的なことを質問したいのであれば、税務署や国税局の電話センターで相談することが可能ですが、節税のアドバイスをしてくれるわけではありません。
広島相続税相談テラスでは、相続に詳しい経験豊富な税理士が多数在籍しており、皆さんのお悩みを解決します。初回相談は無料で対応しておりますので、電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。