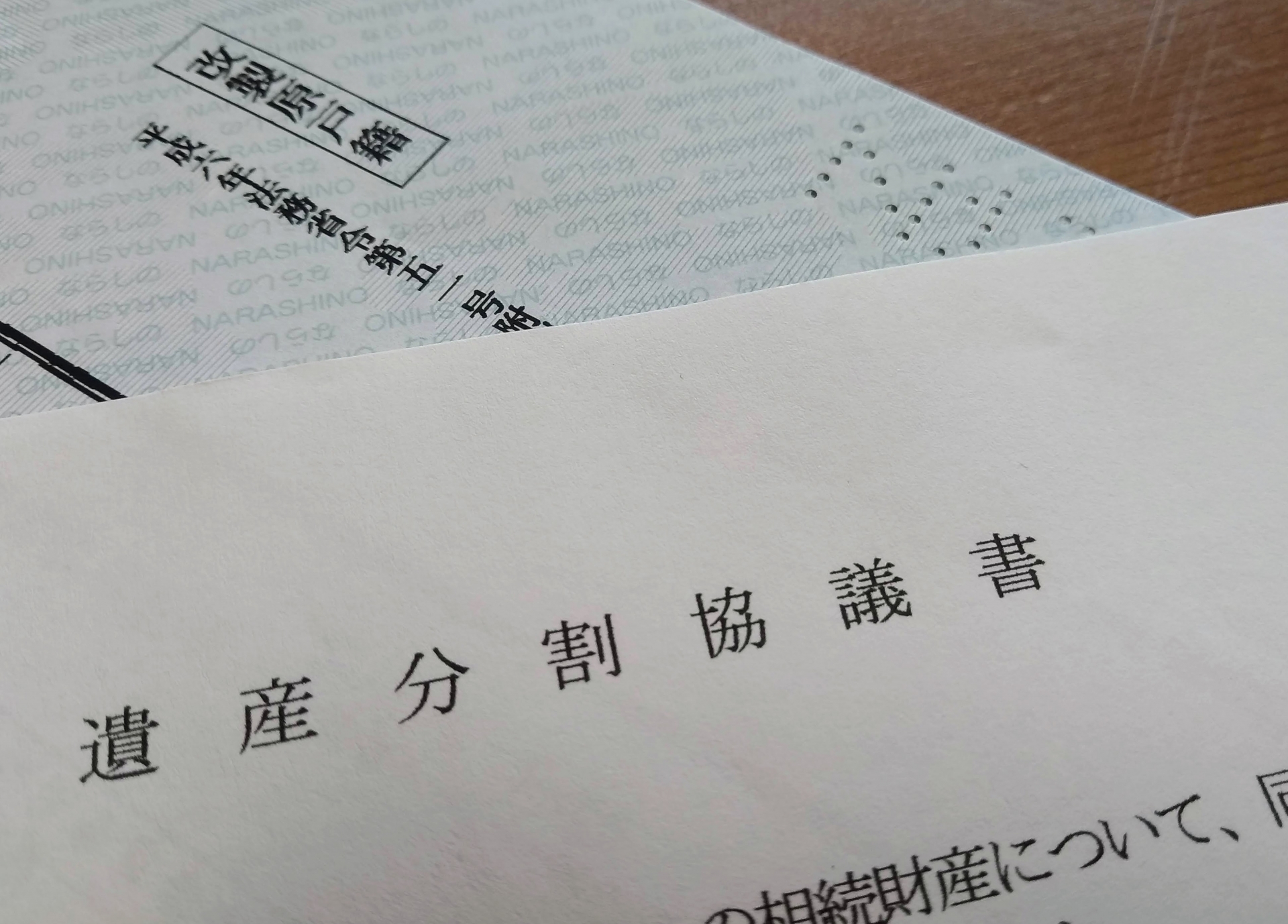相続が発生し、故人が遺言書を作成していない場合、民法で定められた法定相続人全員で亡くなった人の相続財産を分けるための協議を行う必要があります。遺産相続の手続きは一人でも書類の記入などに協力してもらえなければ進めることができません。
しかし、相続人の中にいくら協議への参加を要請してもどうしても応じてくれない人がいる場合どうすればよいのでしょうか。
当記事では実際に遺産分割協議や相続手続きに協力してくれない人がいるケースの対処法についてポイントをおさえて解説します。
相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要がある
相続が発生すると法定相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議を成立させ、書面を作る必要があります。
遺産の分割方法が決まっていないと土地・建物の登記や金融機関の名義変更もできません。遺産分割協議書は相続人全員で話し合いを行い、分割方法に全員が納得して合意しているという証拠になります。
遺産分割協議書には署名・押印が必要ですので、それぞれの意見がまとまらない場合や相手側に連絡をしても返事が無い状況だからと言って、相続放棄をしたものとして無視して勝手に手続きを進めることはできません。特に配偶者や子供など遺留分がある者から遺留分を侵害された分について請求されるリスクが生じます。遺留分を請求された場合は、基本的に拒否することはできず、遺留分相当額を支払う必要があるので注意が必要です。
過去に親戚同士でトラブルになったことがある場合や、海外など遠方に住んでいる人がいる場合、相続人が多い場合等は問題が起こり手続きが進まない可能性が高いため早めに準備を進める必要があります。
また、連絡を取ったことが無い相続人がいる事例も多いですが、戸籍謄本を辿って連絡をとるなど様々な手段を使って連絡を取る必要があります。
遺産分割協議が完了しないことで生じるデメリット
遺産分割協議の交渉が難航し、完了しないことでどのようなデメリットが生じるのでしょうか。具体的に解説します。
相続税の特例が使えなくなる
相続税の申告期限は原則、相続発生の翌日から10ヶ月以内と決められており期限内に財産の評価や相続税の計算を行い、申告書を税務署に提出する必要があります。
小規模宅地の特例や配偶者控除などの各種特例は相続税の申告期限内に納税を完了させることが前提となっており、期限が過ぎると特例を利用できなくなる可能性があります。
また、相続税の申告期限を過ぎてしまうと加算税などのペナルティが課されるため相続する割合などが決まっていなければ、一旦法定相続割合で分けたものとして相続税の申告を行う必要があります。
次の相続が発生し、更に複雑化する可能性がある
被相続人の配偶者や兄弟が相続人となる場合は比較的年齢も近く、次の相続が発生する可能性があります。相続人が亡くなってしまうとさらに複雑化する可能性もあるため、遺産分割協議が進みにくくなります。
財産を売却することができない
被相続人が死亡した後は不動産などの財産は相続手続きが完了しないと相続人が売却し現金化することができません。売却ができないと固定資産税などの費用も毎年かかりますし、同居していた人がおらず空き家となった場合、建物の老朽化など状態が悪化し、他人に被害が及びそうな場合は補修も行わないといけません。
遺産分割が終わらないことで、財産が放置されて、費用がかさむケースも多くあります。
寄与分・特別受益には時効がある
相続の割合を決める時に寄与分や生前贈与などの特別受益によって配分が変わる場合があります。しかし、特別受益や寄与分の時効は10年と定められており、時効を過ぎると主張ができなくなり、法定相続分で分けることになります。
遺産分割協議に対応してもらえない人がいる場合の対処方法
当事者どうしで連絡を取っても対応してくれない人がおり、手続きを進めることが難しい場合、家庭裁判所での調停や審判を申し立てることで、法的に相手方に遺産分割協議への参加を要請することができます。遺産分割調停の申し立てを行うことで、家庭裁判所から呼出状が送付され、協議への参加が要請されます。このような法的制度を活用することで、解決できることは多いため有効な手段といえるでしょう。
それでも、参加しなかった際は遺産分割審判に移行し、裁判所が法定相続分や事情を考慮して配分の方法を決めることになります。審判を経ることで配分が決定するため、不動産の登記や銀行口座の名義変更を進めることができます。
相続開始後、相続人と連絡をとっても手続きが進まない場合や親族同士が対立してしまい進めることができない場合は直接話し合うよりも弁護士や法律事務所に相談し、法律の則った手段についても検討してみると良いでしょう。
生前の対策が重要
自分の相続が発生した時に財産を受ける家族が困らないようにするためには相続が発生する前に最終的に残った財産を誰に何を遺すか遺言書を作成しておくことが重要です。遺産の配分の内容はもちろんのこと財産の一覧をつけておくことで財産を特定することができますし、配分を決めるに至った理由も書いておくと相続人の納得感も高まるでしょう。ただし、自筆証書遺言の場合、形式不備により無効となる可能性もあります。公正証書遺言であれば、形式不備で無効となることはありません。そのため、できれば公正証書で作成しておくことをおすすめします。
また、遺言の執行者を指定しておくことも大切です。執行者とは遺言の内容を実現する人のことで執行者は預金の解約や名義変更を単独で行うことが認められています。執行者には相続人の中で指定することもできますし、他に司法書士など専門家に先に費用を支払い依頼することも可能です。
専門家に依頼することで知識のある人がスムーズに手続きを行ってくれますし、相続人同士が疎遠な場合は第三者が行ってくれるということは相続人の負担の軽減につながり大きなメリットとなります。
困った場合は専門家に相談を
遺産相続に関するお悩みはさまざまで、手続きの流れの中で不明点やトラブルが起こることも多々あります。相続人同士で関係が悪化し、お互いに感情的になった時はまとめにくくなりますので、第三者に間に入ってもらうことも重要です。
相続について困ったことがある場合は弁護士、司法書士、税理士等の専門家に相談し、アドバイスをもらい、進めるようにしましょう。
特に預貯金、株式や不動産など、課税対象となる財産が基礎控除を超える場合は税金の申告が必要です。相続税の申告は複雑ですが、相続税に強い税理士にサポートを依頼することも可能です。
広島相続税相談テラスでは初回の相談無料でみなさまのさまざまなお悩みに対応しております。お悩みや不明点がある場合はメールやお電話などでお気軽にご連絡ください。