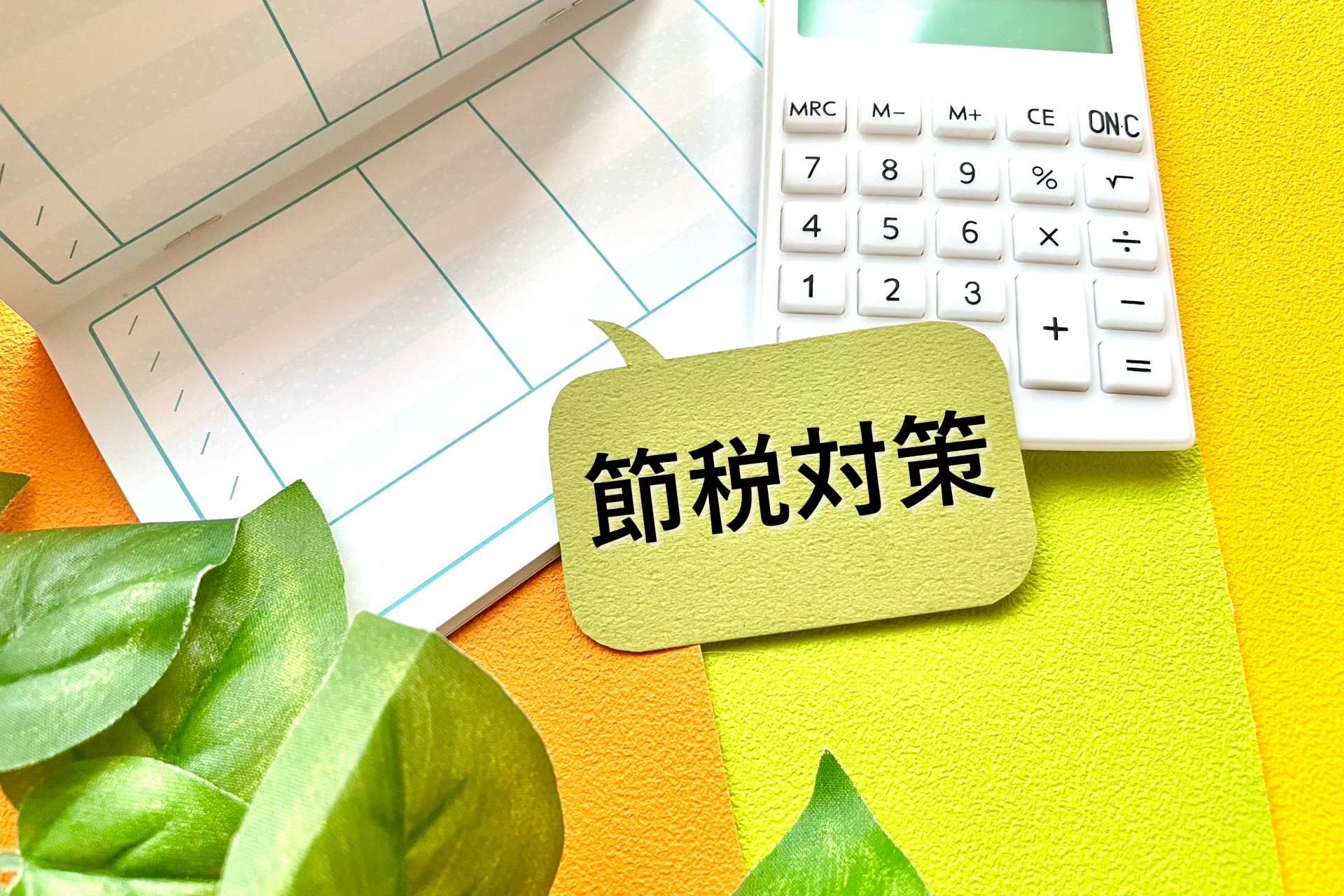相続が発生すると通常は相続人が遺産を整理し、法定相続分を参考に財産を分けることになります。
相続人が財産を取得すると遺産相続する額に応じて相続税がかかる場合があります。
税金の負担をできるだけ軽減したいと考える人は多いと思いますが、節税をするために具体的に何をすれば良いかわからないという人も多いのではないでしょうか。亡くなってから出来ることは少ないので、事前に対策を検討する必要があります。
当記事では相続税の負担を減らすための具体的な方法と注意点などのポイントを解説します。
まずは現状把握
相続税を減らす前に必要なことは現状把握です。
まず相続税の計算の流れとしては銀行に預けている預貯金、株式などの金融資産、土地・建物などの不動産、金やプラチナ、美術品などの現物資産等、あらゆる課税対象となる価値を評価します。土地は路線価、家屋については固定資産税評価額で評価を行います。財産をまとめた総額から基礎控除(計算式:3,000万円+法定相続人×600万円)を差し引いた金額を民法で定められた法定相続割合で分割したものとして相続税の計算を行います。
そのため、各財産の内容に応じて評価を行うことや、法定相続人の人数を確定させることが必要となり、基礎控除を超える場合は相続税の税務署に申告書の提出が必要となりますが、基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
また、配偶者が財産を取得する場合に使える配偶者控除や自宅不動産を同居親族等が取得する場合に使える小規模宅地の特例を利用することで負担を減らすことができます。
節税対策の方法によっては時間がかかることもありますので、生前でも高齢になってから行っても希望通りにはできない可能性もあります。そのため、今後状況が変わるかもしれませんが相続に備えて早めにシミュレーションを行って、現状の税額を算出し、適用できる特例の要件や制度を確認することも大切です。
有効な節税方法
現状の財産の合計と税率を把握することができたら具体的に税金を下げるための対策を検討しても良いでしょう。有効な節税方法と注意点について解説します。
分割方法を決めて遺言を作成しておく
相続税には配偶者控除や被相続人が住んでいた自宅の土地の評価を軽減できる小規模宅地の特例など、取得する人がそのまま住み続けるか等によって利用可否が異なる特例があります。小規模宅地の特例は330㎡まで80%土地の評価額を減額できるため、特に土地の評価が高い地域の場合は実際に支払う税金も大きく減少します。
これらの特例は税金の軽減効果も大きく利用できるか否かで大きく負担が変わります。事前にどのように分ければうまく特例を活用出来るかを検討しておき、遺言書を作成すると良いでしょう。
事前に遺言を作っておくことで、確実に特例を利用できる効率的な配分をすることが可能です。また、相続の権利を持つ者同士で協議をする必要がありません。親が亡くなった時に、兄弟姉妹や他の親族で意見を出し合って揉めるケースも多くあります。遺留分や配分についても、考慮して作成することで相続税を抑えるだけでなく、トラブル防止にも有効です。配分について検討する場合は一次相続と二次相続をふまえて遺産分割の方法を検討することも重要です。
配分について決められない場合は税理士や司法書士などにアドバイスを求めてもよいでしょう。
生命保険の非課税枠を活用する
生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産ですので、本来の相続税の課税対象財産ではありませんが、相続財産に性質が近いものとしてみなし相続財産として課税されます。
ただし、一定の非課税枠が設けられており、生命保険の非課税枠は法定相続人1人あたり500万円で計算を行い、相続放棄をした人がいたとしても人数にはカウントされます。
例えば法定相続人が2人であれば1,000万円、3人であれば1,500万円までは非課税となります。生命保険の非課税枠は簡単で確実に節税ができる方法として有効な手段です。
注意点としては生命保険の商品性によっては加入後、途中で解約できないものや外貨や株式などで、運用するものもありリスクがある商品もあるため、死亡保険金が支払った保険料よりも少なくなってしまう可能性があることです。生活資金として金銭は別に確保しておく必要もありますので、契約時にはデメリットもしっかりと理解してから契約しましょう。
生前贈与を行う
生前贈与は一般的に行われていることの多い節税対策です。暦年贈与での贈与税には基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間で110万円までは非課税となります。
贈与を受ける人は相続人である必要はありませんので、子どもだけでなく、孫や子どもの配偶者など数多くの人に毎年贈与をすることで課税対象の財産を減らすことができます。
また教育資金目的の贈与であれば祖父母などから孫に一括で1,500万円まで贈与が可能です。教育資金の贈与は信託銀行などで専用の口座を作成し、贈与を行い、金融機関から税務署に書類を提出する仕組みになっており、30歳になるまで、教育関連の費用を使う際に払い出すことができます。結婚・子育て用の資金であれば1,000万円まで非課税で贈与可能です。
居住用の不動産を購入するための住宅取得資金の贈与であれば祖父母や父母などの直系尊属から子や孫へ最大1,000万円まで、非課税で贈与をすることが可能です。住宅取得資金贈与の特例は後で、税務署に申告を行う必要があります。税務署から指摘されると贈与税がかかりますので、注意しましょう。
目的によって特例の金額も異なります。資金を大きく減らすことができるケースもありますので、各種特例について確認して利用を検討してみるとよいでしょう。贈与税は頻繁に改正がありますので、最新の情報を確認することが必要です。
特例を活用することで、さらに大きな金額で贈与をすることができ、節税効果を高めることができます。一方で孫の数や住宅購入の有無によって兄弟姉妹間で不公平が生じてしまい、相続が発生した時に残りの財産を法定相続分どおりに分けるとトラブルになりかえって遺族の負担が増えてしまうこともあります。
生前贈与をする場合は相続税を低く抑えることだけでなく、相続人同士の関係にも配慮して行う必要があるでしょう。また、贈与税は税制改正が頻繁にありますので、最新の課税制度を確認しておくようにしましょう。
孫を養子にする
節税策の一つとして孫を養子縁組し、法律上の子どもにするという方法があります。孫を養子にし、親子関係になるメリットの一つは法定相続人を増やすことができることです。法定相続人が増えることで基礎控除と生命保険の非課税枠、退職金の非課税枠が一人分増えることになります。
また、代々引き継いでいる土地などの資産を遺す場合は子どもに相続するよりも孫に財産を遺した方が一代飛ばしで渡すことになりますので、高い節税効果を得られる可能性があります。
ただし、孫等が財産を取得する場合は、実子以外の人を養子縁組を行っていても、相続税の2割加算の対象となります。また、マンションやアパートなどの不動産のみ引き継ぐ場合は、相続税を現金で支払う必要があります。相続開始時に1億円を超えるような不動産を引き継いだ場合、税金の負担も大きくなりますので、現金もあわせて相続させないと相続税が払えなくなってしまう可能性があります。
不動産を購入する
不動産については土地は路線価方式の場合、路線価×面積、建物は固定資産税評価額で評価を行いますが、一般的に土地は時価の8割程度、建物の評価は時価の5割から6割程度の評価になることが多いです。また土地の上に建物を建築しており、賃貸用の物件の敷地となっている土地なら、貸家建付地として更地よりもさらに評価額が下がる制度となっています。
そのため、現金を収益用の不動産に換えることで評価額が下がり、相続税も下がることが多いです。土地を保有している場合は、借入を起こし、マンションやアパートなどの建物を建てることも有効な手段です。債務はマイナスの財産として積極財産から差し引くことが可能です。
債務については不動産から得られる収入からコツコツと返済することになりますが、入居者が思ったように入らなかった場合や金利が上昇し、負担が大きくなるなど事業として賃貸経営がうまくいかない可能性もあり、税額の軽減の効果も大きいもののリスクも大きい方法です。不動産を活用した節税を検討する場合は、夫婦間や子どもなど財産を受け取る可能性がある家族とも相談して選択した方がよいでしょう。
相続税のお悩みは税理士に相談を
上記に税負担を減らす方法について解説しましたが、相続税は頻繁に改正もありますので、国税庁のサイトなどで相続税法の最新の情報を入手して亡くなる前に節税策を考えることが重要です。しかし、特例等の利用条件を満たすかを判断することは一般の人にとって簡単なものではありません。また、今回解説した以外にも節税効果とデメリットもしっかり把握して行う必要があります。
知識や経験がなく自分で申告を行うことに不安がある場合は税務の専門家である税理士にサポートを依頼し、不動産の価額や現物資産の時価などを調べておき事前にシミュレーションを行うことでさまざまな節税対策を実施できますので大きく負担を軽減することが出来るでしょう。
また、相続発生時には原則死亡の翌日から10ヶ月以内と短い期間で申告と納税を完了する必要があります。間違った金額で申告した場合は税務調査で指摘され、ペナルティを課される可能性があります。
期限を守るために事前に準備を行い税理士にもサポートを依頼しておくことで安心して手続きを進めることができるでしょう。
広島相続税相談テラスでは初回は無料でさまざまな相談に対応しています。相続税だけでなく、相続に関するお悩みがある場合は電話やメール等でお気軽にご連絡ください。