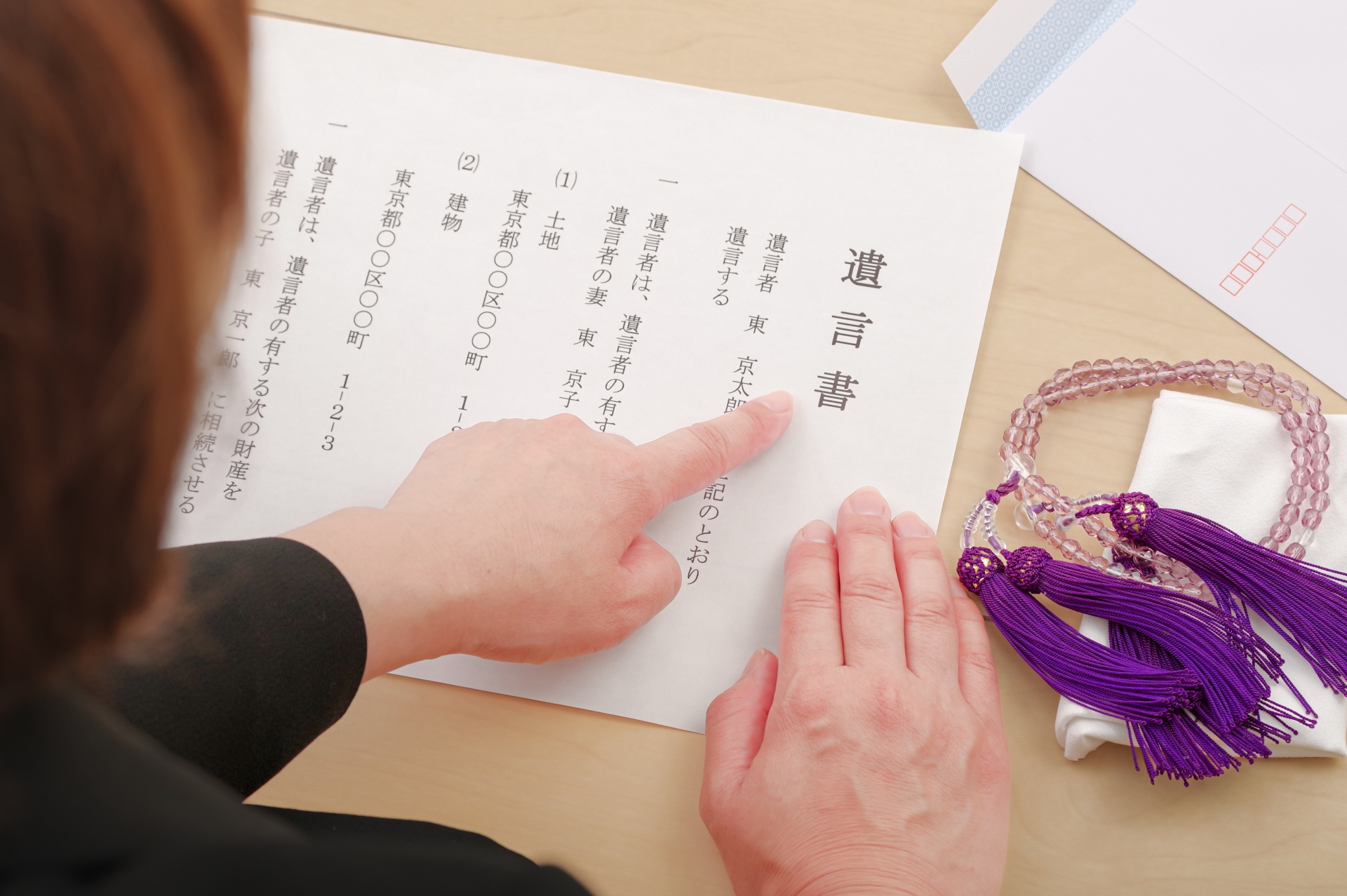相続が発生すると、基本的に民法で定められた法定相続人で話し合って遺産を分割することになります。しかし、遺言書がある場合は、遺言の内容によって財産を分割することになります。
遺言の内容によっては相続人以外の人に遺産を遺す内容となっている場合があります。遺言により相続人以外の人が相続財産を取得する際の相続税やその他、知っておくべき注意点について解説します。
相続税は2割加算となる
遺言書を作成しておくことで相続人以外の人に財産を遺す場合でも被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、相続税の申告が必要となります。遺言を書く際は預貯金や株式、土地・建物など自身が保有する財産を合計し、基礎控除を超えているか確認しておきましょう。基礎控除の計算式は3,000万円+法定相続人×600万円です。
相続税がかかる場合はどれくらいかかるか事前に計算をしておく方がよいでしょう。
また、被相続人の配偶者と一親等の親族以外の者が財産を取得する場合は通常の相続税よりも2割加算となる制度となっています。
相続人以外の人に不動産等、現物資産を遺贈する場合は、相続税の納税のために、もともと自分が保有していた現金を支払う必要が生じるケースもあります。財産を受ける側にも負担がかかりますので、事前に財産の評価額などの情報を伝えておくようにしましょう。
事前の情報を伝えても納税するための資金を確保することが難しい場合は現金を事前に贈与しておくことも選択肢の一つとなります。贈与税には基礎控除があり、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。毎年贈与した資金を貯めておき、現金で納付するための対策にするという方法もあります。現金を贈与しておくことで財産の総額を減らすことができますので、節税にもなり、負担の軽減にもつながります。
配分でトラブルにならないよう注意が必要
遺贈により財産を法定相続人以外の人に遺贈する場合は、遺産分割をする際にトラブルにならないように注意が必要です。
財産を遺す理由があり、相続人も納得しているのではあれば、問題ありません。しかし、財産を取得する受遺者が法定相続人にとって関係が薄く納得いかない人に多額の遺贈である場合、協議をしなくても法定相続人と受遺者の間でトラブルになる可能性も高いでしょう。また、配偶者や子どもには遺留分があります。遺留分を侵害した遺言を作成しても遺留分を請求されるとその通りに配分することができません。
遺言を作成する際は細かく各種財産の取得する人を指定することはできますが、法定相続分とあまりにも異なる配分となるとトラブルになる可能性も高いので注意が必要です。
遺言を作成する際は執行者を指定することもできます。執行者とは遺言どおりに財産の配分の手続きをする人のことで相続人を指定することもできますし、司法書士など知識がある第三者に依頼することも可能です。自分が亡くなった後に受遺者と相続人の接触をなるべく避けたい場合は、執行者を指定しておく方が良いでしょう。
また、遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証役場で作成する遺言で遺言書の原本は公証役場で保管されます。そのため、法律上有効であることが作成時に確定し、偽造や変造の可能性はありません。
一方で自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があり、不備があると法的な効力がなくなる可能性があります。そのため、確実に有効な遺言書を遺すために公正証書遺言で作成することをおすすめします。
相続税の申告は税理士に相談を
相続税の申告は課税の対象となる各財産を評価し、一覧の表にまとめて、税金の計算を行う必要があります。相続税の計算は非常に複雑で、一般の人が初めて行う際は自分で行うことは大変です。また、被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内と期限も短いため、早めに準備をすることが大切です。
財産の評価や計算方法が分からない場合は、費用はかかりますが税務の専門家である税理士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。誤って申告した場合、税務署から税務調査で指摘される可能性もありますので正確に申告をする必要があります。
広島相続税相談テラスでは初回の相談は無料で対応しております。不明点や質問がある場合はお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。